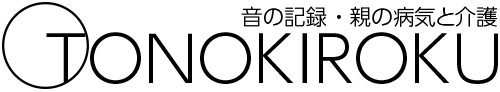目次
第7話|在宅生活のはじまり——家が“治療の場所”になるということ
退院の日程が決まったとき、ほっとする気持ちと同時に、胸の奥に静かな不安が生まれました。
母が戻る場所は、長年ひとり暮らしを続けてきた実家です。
けれど、その家は、在宅で療養する環境とはとても言えませんでした。
足の踏み場がない、というほどではないにしても、
介護用ベッドを置くことなど想像もつかない——
まずは、私たち姉妹が座る場所をつくるところから、という状態でした。
母は、これまで自分で布団を上げ下げして寝ていました。
年齢を考えれば決して楽ではなかったはずですが、
「まだできるから」と手放さずに続けてきた習慣です。
しかし今回ばかりは、とても現実的ではありませんでした。
そこで、退院を見据えて最初に決めたのが、介護用ベッドの購入でした。
「布団はもう大変だから、ベッドにしようか」
そう伝えると、母は表情を明るくし、病室で何度も言いました。
「ベッドはもう来たかい?」
「いつ届くんだろうねぇ」
まるで、初めて自分の部屋を持つ子どものように。
その無邪気さに、私たちは少し救われた気がしました。
ベッドの設置には、まず“空間”をつくる必要があった
母が楽しみにしている以上、退院までにベッドを設置したい。
けれど、現実の実家は、ベッドどころか、
ベッドを置くための「空間」そのものを生み出す段階からでした。
退院までの二週間。
私たちの一日はほとんど同じような流れでした。
朝、それぞれの家庭の家事をこなし、
仕事に行くか、あるいはスケジュールを調整し、
昼には病院へ向かい、母の様子を見て洗濯物を預かる。
夕方に病院を出る頃には、体も心も重く、
「今日はここまでにしようか」と一瞬思うのですが、
その足で実家へ向かい、そこからが“第二の仕事”の始まりでした。
部屋というより、“母の時間そのもの”が積み重なっていた
片づけを始めると、棚、引き出し、紙袋の中、
どこを開けても、母の「いつか使うから」が静かに出てきました。
新品のハンカチ、溜めておいたスーパーの袋、
古い鍋、読みかけの新聞、使いかけの薬、
いつの間にか重なっていた段ボール箱。
ひとつひとつ手に取るたびに、
「これ、母が大事にしてたものかもしれない」
「これは捨てていいのかな」
そんな迷いが胸をよぎりました。
時々、箱の底から驚くようなものが出てきて、
「なんでここにこれがあるの?」
「え、小銭だけで重さ1キロくらいあるんじゃない?」
と、思わず笑ってしまう場面もありました。
不安が大きすぎると、人間は逆におかしくなるのかもしれません。
これからの生活のこと、母の病気のこと、自分の家庭と仕事のこと。
考えれば考えるほど、行き場のない不安だけが増えていき、
その不安の “あまりの形のなさ” に、
ふっと笑ってしまうような瞬間が何度もありました。
病院と片づけと、それぞれの生活——すべてが同時進行だった
片づけは、決して集中して取り組めるような状況ではありませんでした。
途中で病院から電話が入り、
家に帰れば子どもの送迎、仕事の締切、家族の夕飯。
翌日の段取りを考えながら洗濯物を畳み、
その合間に姉たちとLINEで片づけの段取りを相談する。
不思議なことに、
あの日々の細かな順番は、もう正確には思い出せません。
ただ、常に何かを急いでいて、
それでも終わらず、
とにかく動き続けていたことだけは鮮明に覚えています。
「あれはいつ片づけたっけ?」
「この部屋、どうやって空けたんだっけ?」
今振り返っても、記憶が曖昧なほど、
すべてが同じ色の“必死な毎日”でした。
ベッドを迎える準備は、家の新しい役割をつくる時間でもあった
ようやくベッドを置くスペースが見えてきた頃、
部屋の空気も、どこか変わったように感じました。
窓を開けると、初夏の風が流れ込み、
「母が帰ってくる」という実感が
少しずつ部屋の中に満ちていきました。
「母が帰ってくる」という実感が
少しずつ部屋の中に満ちていきました。
家は、もともと“暮らすための場所”であって、
治療のためにつくられた空間ではありません。
それでも、母が「ここで過ごしたい」と望んだ以上、
この家を少しずつ“治療の場所”に近づけていく必要がありました。
ベッドを設置し、部屋が少し広く見えるようになったとき、
家の中に、新しい光がひとつ差し込んだように感じたのです。
← 第6話|術後の数日間 —— 揺れる気持ちと小さな回復
第8話|在宅か施設か —— 家族で考えた“これからの暮らし方” →