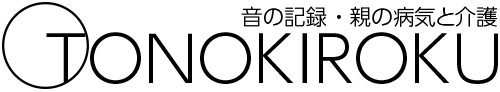目次
第11話|訪問看護が来た日——知らなかった“支える仕事”の存在
どんな介護サービスを受けるのか
家族で悩んだ日々
介護保険の申請を終え、
包括支援センターやケアマネさんとの話が進む中で、
私たちは「どのサービスを利用するのか」という
現実的な選択に向き合わざるを得なくなりました。
当初、私たち姉妹は
デイサービスを利用してもらうことを考えていました。
家族の負担が大きくなり始めていたこと。
ずっと家にいることで母の気持ちが閉塞してしまうのではないか、
という不安があったこと。
そして、
毎日の片づけ・病院との往復・在宅準備に追われ、
私たち自身の疲れが
限界を越えつつあったこと——。
そのどれもが、
「外へ出る機会をつくったほうがいいのでは」と
私たちをデイサービスへと向かわせていました。
けれど母は、
その提案をはっきりと拒みました。
「私は行かないよ。
ああいう所でお世話になるのはイヤ。」
元准看護師として長く介護の現場で働いてきた母にとって、
自分がお世話される側になることは
想像以上に受け入れがたいことだったのかもしれません。
ケアマネの提案と、訪問看護という選択肢
そんな中、ケアマネさんが
母と私たちの様子を見ながら
静かにこう提案してくれました。
「今の状態なら、
デイサービスよりも訪問看護のほうが
お母さまに合っているかもしれません。」
無理に外へ連れ出すのではなく、
家の中で、
母が自分のペースを保ったまま
医療の支援を受けることができる。
その説明を聞いたとき、
私たちの胸の奥にあった
「無理に外へ出そうとしていたかもしれない」
という小さな罪悪感が
静かにほどけていくのを感じました。
母にその提案を伝えると、
反射的に拒むかと思いきや、
少し間を置いて小さく言いました。
「……来てくれるなら、いいかな。」
しぶしぶの承諾でしたが、
それでも母にとっては大きな一歩でした。
訪問看護が家に入る日
訪問看護が初めて来る日、
母はいつもより少しそわそわしていました。
私たち姉妹も、
家に「医療」が入るという事実に、
落ち着かない気持ちを抱えていました。
扉を開けると、
柔らかな表情の看護師さんが立っていて、
その瞬間、家の空気がふっと和らぎました。
看護師さんは
母の表情や声の調子を丁寧に読み取りながら、
深く踏み込まず、
でも必要なところだけ静かに触れていきます。
母が病名を言いたがらないことも、
病状を曖昧に話すことも、
すぐに察してくれたようでした。
「大丈夫ですよ。話せる範囲で十分ですからね。」
その一言で、母の肩から力が抜けていくのがわかりました。
医療と生活が“ぶつからずに並ぶ”ということ
看護師さんが母の状態を確認している間、
家の中の動線や椅子の高さ、
飲み物の置かれる位置まで
さりげなく見ていることに気づきました。
医療を
“生活の中にそっと置いていく”ような優しさ。
病院のような緊張ではなく、
家の空気にあわせて
医療がゆっくりと溶けていくような感覚でした。
家族だけでは支えきれなかった部分に、光が差す
帰り際、看護師さんが
「何かあればすぐに連絡してくださいね」と言ってくれました。
その言葉が、
私たち姉妹が抱えていた
小さな張りつめたものを
静かに解いてくれました。
母を守るための支えが、
私たち家族だけではない——
その安心が胸の奥に確かに灯った日でした。
訪問看護を受けてみた母の気持ち
訪問看護が帰ったあと、
母はベッドに腰掛けたまま
ぽつりとつぶやきました。
「……優しい人だね。
また来てもらってもいいかもしれない。」
最初は頑なに介護サービスを拒んでいた母が、
ゆっくりと心を開き始めていることを感じました。
母の変化はとても小さくて、
でもとても大切なもの。
その始まりが、
この日の訪問看護でした。
← 第10話|ケアマネとの出会い —— “支援者が増える”という安心
第12話|訪問診療をお願いした理由 —— 病院から“医療が家に来る”へ→