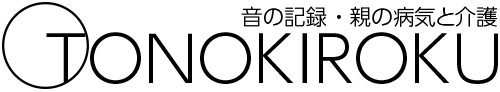第3話|入院の日——母を見送る背中に重ねた思い
入院という始まりの朝
入院の日。
朝、母を迎えに行くと、
自分の体調よりも、家で待つ猫のご飯のことを何度も気にしていました。
「ちゃんと食べられるかしらね」と、少し不安そうに笑う姿が、
いかにも母らしいと思いました。
病院までの道のりを車で向かい、
受付を済ませ、一通りの説明を受け、
看護師さんや担当医の先生と顔を合わせながら、
入院生活の準備が一段落しました。
その後、病棟の談話室に通され、
家族4人で少しだけ腰を下ろしました。
大きな窓から光が差し込み、
病院とは思えないほど穏やかな空気が流れていました。
病棟の談話室で
「せっかくだから写真を撮ろうか」と、誰かが言いました。
スマートフォンを手に、笑顔を作って並んだのを覚えています。
今振り返ると、あの写真の母はまだ少しふっくらしていて、
いつもの笑顔が残っていました。
病院で家族全員がそろって写真を撮るなんて、
あの時が最初で最後なのかもしれません。
帰り道に感じたこと
病室をあとにして、
母が見えなくなるまで小さく手を振りました。
「明日また来るね」と言葉にした瞬間、
声が少し震えたのを自分でも感じました。
母は穏やかにうなずき、
そのまま白い廊下の奥へと歩いていきました。
不思議なもので、
ついさっきまで自宅で見ていた母と、
入院着をまとい、病院のベッドに腰を下ろした母は、
まるで別の人のように“病人”に見えました。
その姿が悲しくもあり、
でもそれが今の現実なのだと、静かに受け止めるしかありませんでした。
病院の外に出ると、空はどこまでも青くて、
初夏の風が頬を撫でました。
けれど、心のどこかに静かなざわめきが残ったままでした。
家に帰る車の中、
助手席には母の鞄の小さな残り香がありました。
それが、不思議なほど安心でもあり、寂しくもありました。
今、思うこと
あの日撮った一枚の写真は、
“日常と非日常の境目”にあったように思います。
母は「入院する人」になり、
わたしたちは「見送る家族」になった。
その小さな境界線が、
これからの時間を静かに変えていきました。
🌿
時間が止まるような瞬間の中に、
それでも笑顔で写っていた母の姿。
あのときの光の柔らかさを、今でも覚えています。