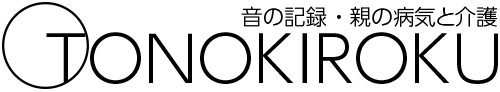目次
第32話|午後の沈黙——生活のリズムが崩れていく
午後の家が、
こんなにも静かだっただろうか——
と思うようになったのは、この頃からでした。
午前中、母は気力を振り絞るように
洗濯物を干したり、新聞をめくったりしていました。
けれど昼食を境に、
その動きは急に細くなっていきました。
まるで午前中の明るさが
午後になると一枚ずつ剥がれるように
母の姿から静かに消えていくようでした。
「午後になると体が動かないのよね」
こたつに入ったまま、
両手を膝の上で揃えて、
母は小さな声でそう言いました。
痛みがあるわけでもない。
息が苦しいわけでもない。
けれど、力が入らない。
「ちょっと横になるね」
そう言って布団に入ると、
しばらく返事が返ってこないことがありました。
眠っているというより、
深いところに沈んでいくような静けさ。
聞こえてくるのは、
時折ふわりとした寝息だけ。
午後の部屋は、
まるで時間がゆっくり沈んでいくような
独特の気配に包まれていました。
生活のリズムが、音を立てずに崩れていく
午後の動けなさは
一日の流れを大きく変えました。
夕食の準備をしようと声をかけても、
起き上がるまでに長い間が空くことが増えました。
キッチンに一緒に立つこともなくなり、
「味見してみる?」と聞いても
「あとでいいわ」と答える日が続きました。
食べる量も、
昨日よりさらに少なく、
味噌汁を数口だけで終えるようになりました。
それらひとつひとつは小さな出来事ですが、
生活の輪郭がゆっくりと薄くなっていくようにも見えました。
家の音が少なくなるという変化
午後の家では、
以前なら当たり前に聞こえていた生活音が
ふっと消えていました。
新聞をめくる音、
庭の戸を開ける音、
湯を沸かす音。
そのどれもが消えた時間は、
例えるなら——
家の中に“沈黙の層”ができたような感覚。
静かなのに、
その静けさに意味があるように思えて
胸の奥がざわつくこともありました。
私はその沈黙を、
まだ深刻に捉えないようにしながらも、
どこかで確かに感じ取っていました。
「何かが変わり始めている」
という、言葉にならない気配。
変化は突然ではなく、静かに積み重なっていく
午後の沈黙は、
体調の急変ではありませんでした。
むしろ、
一日の中に忍び込むように
少しずつ広がっていく“影”のようなものでした。
午前と午後の差が
日に日に大きくなっていく。
生活のリズムが
音もなく傾いていく。
それは、
“今日だけのこと”でも
“様子を見れば戻るもの”でもないのでは——
と、
胸のどこかで思い始めた頃でもありました。
夕方の薄暗がりの中で座る母の姿は、
どこか遠くを見ているようにも見えました。
その横顔を見つめながら、
私は静かに息を吸い込みました。
この変化と、向き合っていかなければいけない。
そんな思いが、
まだ形にならないまま
胸の奥にじんと広がっていきました。