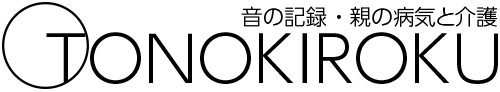目次
第14話|食事の工夫と母のこだわり——日常に戻したい“母の味”
母の食欲が落ち始めたのは、
薬の作用がゆっくりと体に馴染んできた頃でした。
食卓につくまではいつも通りなのに、
箸が思うように進まない日が増えていく。
それでも、母の“食べたいものへのこだわり”は
むしろ強くなっていくように見えました。
「今日はうどんがいい」
「やっぱりご飯が食べたい」
「少しでいいから、あの煮物」
そのたびに台所に立ち、
母の好みに合わせて作るのですが、
実際に出すと、
ほんの数口で止まってしまうことも多くなりました。
母の苦しさもわかる。
けれど、残された食事を前にすると、
どうしても胸がしんと痛くなる瞬間がありました。
そしてふと、
自宅で待つ子どもたちの夕食の時間に
間に合わなかった日のことがよぎります。
急いで作れず、
「今日は冷凍食品でお願いね」と伝えた夜。
母のために台所に立ちながら、
自分の家庭では十分にしてあげられなかったことを思い出すと、
胸の奥がきゅっと痛むような、
なんともいえない「やるせなさ」が込み上げてきました。
日常に戻りたかったのは、母だけじゃなかった
母の要望は、
ただの“わがまま”ではありませんでした。
おそらく、
これまで通りの自分でいたい
という気持ちの表れだったのだと思います。
食べることは、生活の中心で、
母にとっては「元気のバロメーター」のようなもの。
自分で「食べたい」と言えるうちは、
まだ日常がつながっている——
母は本能的にそう感じていたのかもしれません。
けれど、食卓を囲むたびに、
以前との違いが静かに積み重なっていきました。
毎食ごとの工夫と、家族の疲れ
母の体が求めるものは少しずつ変わり、
私たち姉妹が考える「栄養」や「体に良いもの」と
母の「その時食べたいもの」が
なかなか一致しない日が続きました。
その度に工夫して、
その度に作り直して、
その度にまた残って——。
繰り返しの中で、
私自身も知らず知らずのうちに
心のどこかが削られていくようでした。
「食べてほしい」と願う気持ちと、
「また残された」という小さな疲れ。
それが混ざり合って、
食卓の時間が以前とは違う意味を帯び始めていきました。
それでも「母の味」に近づけたくなる
不思議なもので、
母のために作った料理が残される日が続くほど、
「今度こそは食べてもらいたい」と
頑張ってしまう自分がいました。
母が昔つくってくれた味——
煮物の甘さ、
お味噌汁の塩加減、
卵焼きのやわらかさ。
できるだけ近づけたくて、
台所に立つたびに
その“母の味の記憶”が背中を押してきました。
でもその努力が必ず報われるわけではなく、
母の体調次第で箸は止まり、
残されたお皿を前にして
「今日は仕方がない」と自分に言い聞かせる日が増えていきました。
食卓は、母の変化をいちばん正直に伝えてくる場所だった
食事の量、味の好み、気分、表情。
すべてが日によって違う。
その揺れを、
1日3回、私たちは直接受け止めることになります。
体調の変化が言葉より早く、
母の生活の声になって表れる——。
それが、
この頃の食卓の空気でした。
食事を作ること。
食事を残されること。
そして、食卓に並ぶ“いつもと違う表情”。
どの瞬間も、
母の変化をいちばん近い距離で見つめる時間だったのだと思います。
小さな困難と、小さな優しさで続いていく日々
食事は、毎日続いていくものです。
母の体調、母の気分、家族の疲れ、
その全部を抱えながら、
それでも食卓は一日も欠かさず訪れます。
完璧にはできなくても、
母が少しでも「食べたい」と思う瞬間を大切にしたい——
そう思いながら、
ひとつひとつの食事を紡いでいきました。
食事はただの栄養ではなく、
母にとっても、私たちにとっても、
変わっていく日常を確かめる“鏡”のようなものでした。
← 第13話|薬の調整と副作用——小さな変化が生活全体に広がる
第15話|宅配弁当という選択——便利さと“口に合わない”現実 →